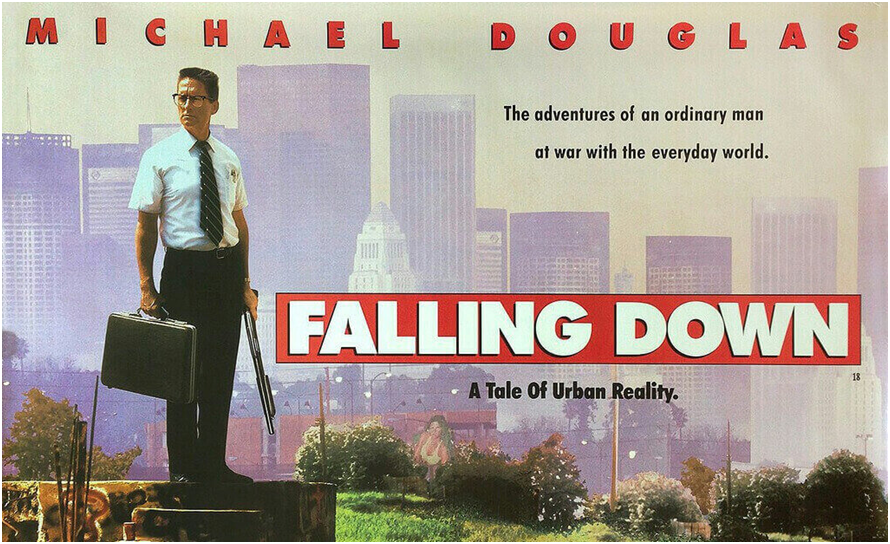文豪名鑑05-自らの思想をスケッチする作家、夏目漱石。
- 日本文学
掲載日: 2023年05月17日
並みいる明治時代の文豪のなかでも、ずば抜けて人気のある作家が夏目漱石です。
なにしろ、明治時代に発表された「吾輩は猫である」や「坊ちゃん」は、いまだに人気がありますし、「こころ」に至っては現在の作家の刊行物に交じって今でも販売部数を伸ばしています。
その人気の秘密を探っていきましょう。
夏目漱石ってどんな作家?
一見すると冗長な人物描写をだらだらと書き繋げていて、退屈で読み進めるのが苦痛に感じる方もいるやもしれません。
芥川龍之介の作品の方が、展開が早くて面白い!と思う方もいるでしょう。
では、なぜ、芥川龍之介をはじめ多くの作家が門下生となって夏目漱石を慕っているのでしょう。
夏目漱石が描いているのは、ストーリーではないのです。
描いているのは登場人物の細やかな生活です。
作品を一度でも読むとよくわかるのですが、くどいぐらいにだらだらと登場人物の生活の様子が描き重ねています。
登場人物の生活を描き重ねることで、登場人物が俄かに存在感を増し現実の人物であるかようなリアルさで動き出すのです。
フランスの文豪、バルザックの様な描き方です。バルザックの文章もやたら長いのです。
漱石の凄いところは、それだけにとどまらないところです。
そこに、漱石の思想が入ってきます。
つまり、リアルな人物を使って漱石の思想を語る、というわけです。
こんな芸当ができる作家は他にいません。
そんな夏目漱石の人生を見ていきましょう。

「愛」に恵まれなかった子供時代。
夏目漱石は、1867年(慶応3年)に江戸 牛込馬場下に生まれます。
江戸の牛込から高田馬場までの一帯を治めていた名主である父・直克と、母・千枝の5男として、とても裕福な家庭で育ちます。
ところが、明治維新の煽りを受け、没落の憂き目に会うのです。
そんな状況ゆえ、漱石は生まれて間もなく知人の古道具屋に里子に出され、
さらに、夏目家の書生一家、塩原昌之助に養子に出されてしまいます。
紆余曲折があり、漱石が生家に戻るのは9歳の時。
その間はずっと、父母の愛情に触れずにいたのです。
漱石の心情は、「夢十夜」-第九夜(父が戦に行ってしまう話)によく表れています。

色々な事情があったにせよ、漱石は名主の家柄で育てられています。
「名主」は、その地域の行政、治安の維持を司る地位。
町人ではあっても名字帯刀も許される武家に近い階級です。
そのためきちんとした倫理観を教え込まれています。
漱石の作品には、公序良俗に反するような事柄はあまり描かれません。
確固たる倫理観につら向かれているのは、幼い頃からの環境の賜物ではないでしょうか。
煩悶の時代を迎える。
1884年(明治17年)、17歳になり大学予備門予科(帝国大学の予備機関)に入学します。
学業では、すべての科目で主席であり、特に英語に秀でていました。
そして、1889年(明治22年)、同窓生である正岡子規と出会います。
子規のペンネームの一つである「漱石」を譲り受け、以降は「漱石」名を使うことになります。
1890年(明治23年)、正岡子規と共に、創設間もない帝国大学英文科に入学。
が、しかし、大学生時代の漱石には苦悩があります。
漱石は学習院大学での講演で、当時の苦悶について、こんな風に言及しています。
私は大学で英文学という専門をやりました。
それを三年専攻した私にも何が何だかまあ夢中だったのです。私はその先生の前で詩を読ませられたり文章を読ませられたり、作文を作って、冠詞が落ちていると云って叱れたり、発音が間違っていると怒れたりしました。
試験にはウォーズウォースは何年に生れて何年に死んだとか、シェクスピヤのフォリオは幾通りあるかとかいう問題ばかり出たのです。文学とはどういうものだか、これではとうてい解るはずがありません。
それなら自力でそれを窮め得るかと云うと、まあ盲目の垣覗きといったようなもので、図書館に入って、どこをどううろついても手掛がないのです。これは自力の足りないばかりでなくその道に関した書物も乏しかったのだろうと思います。
とにかく三年勉強して、ついに文学は解らずじまいだったのです。私の煩悶は第一ここに根ざしていたと申し上げても差支ないでしょう。
「私の個人主義」青空文庫
このような状況にあった漱石は、神経衰弱に陥っていくのです。
実は大学入学前の1887年(明治20年)に長兄・大助、次兄・栄之助と死別。
さらに1891年(明治24年)には三兄・和三郎の妻の登世と死別しています。
次々に近親者を亡くしたことも、漱石の精神状態に暗い影を落としたのではないでしょうか。
特に淡い恋心を抱いていた登世への想いは、「夢十夜」第一夜(死にゆく女を看取る男の話)に見て取ることができます。

さて、大学時代の漱石は、夏期休業を利用して同窓生の正岡子規の松山の実家を訪ねます。
その際に、当時15歳の高浜虚子と出会っています。
1893年(明治26年)、漱石は帝国大学を卒業します。
最初の職業は、高等師範学校の英語教師です。
ただ、漱石の神経衰弱は悪くなる一方です。
日本が西洋化に突き進むことをよく思っていない漱石。
ましてや、英語を日本人に教えることに違和感を抱いていることも漱石が苦悩する一因だったのでしょう。
とうとう高等師範の方へ行く事になりました。
しかし教育者として偉くなり得るような資格は私に最初から欠けていたのですから、私はどうも窮屈で恐れ入りました。もっと横着をきめていてもよかったのかも知れません。しかしどうあっても私には不向な所だとしか思われませんでした。
「私の個人主義」青空文庫
奥底のない打ち明けたお話をすると、当時の私はまあ肴屋が菓子家へ手伝いに行ったようなものでした。
鎌倉の円覚寺で座禅を組むなどしましたが、効果は得られなかったようです。
その時の心境は、「夢十夜」-第二夜(悟りを開く侍の話)に、実によく表れています。

そんな東京での生活に嫌気がさしたのか、1895年(明治28年)、東京から逃げるように高等師範学校を辞職し、子規の故郷でもある愛媛県松山市の尋常中学校に英語教師として赴任します。
一年の後私はとうとう田舎の中学へ赴任しました。それは伊予の松山にある中学校です。
「私の個人主義」青空文庫
あなたがたは松山の中学と聞いてお笑いになるが、おおかた私の書いた「坊ちゃん」でもご覧になったのでしょう。
「坊ちゃん」の中に赤シャツという渾名あだなをもっている人があるが、あれはいったい誰の事だと私はその時分よく訊かれたものです。
誰の事だって、当時その中学に文学士と云ったら私一人なのですから、もし「坊ちゃん」の中の人物を一々実在のものと認めるならば、赤シャツはすなわちこういう私の事にならなければならんので、――はなはだありがたい仕合せと申上げたいような訳になります。
松山では、子規とともに俳句の佳作を残しています。
松山での暮らしを基にして書かれた作品が有名な「坊ちゃん」です。
さて、翌1896年(明治29年)、漱石は熊本市の第五高等学校(今の熊本大学)の英語教師として赴任します。
熊本で、漱石は結婚をします。お相手は貴族院書記官長・中根重一の長女・鏡子。
そのころの心境を漱石は、講演で語っています。
松山にもたった一カ年しかおりませんでした。
立つ時に知事が留めてくれましたが、もう先方と内約ができていたので、とうとう断ってそこを立ちました。
そうして今度は熊本の高等学校に腰を据えました。
熊本には大分長くおりました。突然文部省から英国へ留学をしてはどうかという内談のあったのは、熊本へ行ってから何年目になりましょうか。
私はその時留学を断ことわろうかと思いました。
それは私のようなものが、何の目的ももたずに、外国へ行ったからと云って、別に国家のために役に立つ訳もなかろうと考えたからです。しかるに文部省の内意を取次いでくれた教頭が、それは先方の見込みなのだから、君の方で自分を評価する必要はない、ともかくも行った方が好かろうと云うので、私も絶対に反抗する理由もないから、命令通り英国へ行きました。
「私の個人主義」青空文庫
かくして、1900年(明治33年)、英語教育法研究のため、文部省より英国留学を命じられます。
ロンドン着任後の漱石は、苦悩の日々を迎えます。
その時の心境は以下の如しです。
いったん外国へ留学する以上は多少の責任を新たに自覚させられるにはきまっています。
それで私はできるだけ骨を折って何かしようと努力しました。
しかしどんな本を読んでも依然として自分は嚢の中から出る訳に参りません。
この嚢を突き破る錐はロンドン中探して歩いても見つかりそうになかったのです。私は下宿の一間の中で考えました。つまらないと思いました。
「私の個人主義」青空文庫
いくら書物を読んでも腹の足にはならないのだと諦めました。
同時に何のために書物を読むのか自分でもその意味が解らなくなって来ました。
ロンドンでの生活が一年ほど経過し、封建的な考えが支配する日本人とは違う、自由なロンドンの人々の考えに触れる漱石。
そこで会得したものがあります。それは「自己本位」という考え方。
根本的に自力で作り上げるよりほかに、私を救う途はないのだと悟ったのです。
今までは全く他人本位で、根のないうきぐさのように、そこいらをでたらめに漂よっていたから、駄目であったという事にようやく気がついたのです。たとえば西洋人がこれは立派な詩だとか、口調が大変好いとか云っても、それはその西洋人の見るところで、私の参考にならん事はないにしても、私にそう思えなければ、とうてい受売をすべきはずのものではないのです。
私はこの自己本位という言葉を自分の手に握ってから大変強くなりました。
今まで茫然と自失していた私に、ここに立って、この道からこう行かなければならないと指図をしてくれたものは実にこの自我本位の四字なのであります。かく私が啓発された時は、もう留学してから、一年以上経過していたのです。
「私の個人主義」青空文庫
それでとても外国では私の事業を仕上しあげる訳に行かない、
とにかくできるだけ材料を纏めて、本国へ立ち帰った後、立派に始末をつけようという気になりました。
斯くして漱石は、1903年(明治36年)に英国留学から帰国するのです。
帰国後はすぐに、東京帝大の講師の職に就きます。
が、ここに来て、またもや漱石を悩ます出来事が降りかかってきます。
前任者であった小泉八雲の講義があまりにも素晴らしかったため、小泉八雲を引き留める運動が起こったり、漱石の講義の不平不満が湧き起こったりしたのです。
そんな境遇の漱石は苦悩のあまり、神経衰弱を患うに至ります。
作家、夏目漱石の誕生。
1904年(明治37年)、神経衰弱を患う漱石の様子を見かねた友人の高浜虚子は、少しでも症状を軽くできるのではないかと考え、漱石に小説の執筆を勧めます。
それを受けて漱石は、自宅に迷い込んで住み着いてしまった猫を題材にして小説を執筆します。
翌年、「ホトトギス」に発表された作品が「吾輩は猫である」です。
漱石、37歳の時のことです。
さらには、1906年(明治39年)には「坊つちやん」を「ホトトギス」に発表。
同年、「草枕」を文芸誌「新小説」に発表しています。
明治末期は、文学の主流といえば「自然主義文学」です。
創作を一切交えずに、作家本人の人生を赤裸々に正直に描く作品を良しとしていました。
そんな風潮の最中に、漱石は「反自然主義」の姿勢を貫きます。
創意工夫をふんだんに盛り込んで、自らの思想を作品で語るのです。
「吾輩は猫である」に至っては、猫が喋ります。
漱石は、高浜虚子「鶏頭」の序文に余裕のある作品とは、どんな作品か、を書き記します。
そんな漱石の小説は、文壇からは一段低く評価され、侮蔑的な意味を込めて「余裕派」とよばるようになるのです。
「余裕派」の作家は、高浜虚子、正岡子規、漱石門下の寺田虎彦などがいます。
封建的な考え方、つまり人に指南されて動く人生では何も見いだせなかったが、一度そこから離れて客観的に自分の考えで思考する「自己本位」の立場に立って、自分を取り戻すことができた漱石。
その姿勢こそが、余裕派たるゆえんです。
余裕派としての漱石の姿勢は「草枕」を読むと、リアルに伺えます。
「草枕」の主人公の画家は、旅を通じて芸術についての思索を深めていきます。
そこには、頭では余裕を持ちたいと思ってはいても、実際はそうそううまくはいかないそんな漱石の生きざまがリアルに描かれています。
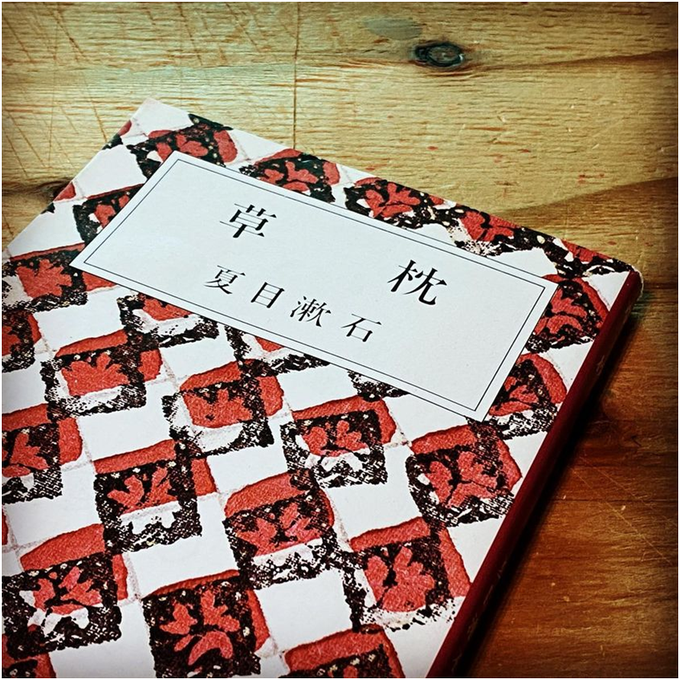
職業作家として歩みだす。
1907年(明治40年)、朝日新聞社に入社し、新聞社付きの作家となります。
これまでは、帝大の講師の傍らに小説を書くというスタンスでしたが
どうしても講師の仕事に我慢がならなかったのでしょうか、講師を辞め小説だけに専念することに。
これ以降は朝日新聞への連載という形で小説を発表しました。
最初の連載作品は「虞美人草」です。
翌1908年には「夢十夜」、つづいて「三四郎」を連載します。
「坊ちゃん」は、都会から田舎へやって来た学生の体験をユーモアたっぷりに描いています。
そして、「三四郎」は、その逆、田舎から都会へやって来た学生の体験を、やはりユーモアたっぷりに描いています。
思わせぶりな最期が気になった読者の要望にこたえる形で続編を連載することになります。
題名は「それから」。
新聞紙上に漱石が書いた予告文が掲載されています。
色々な意味に於てそれからである。「三四郎」には大学生の事を描いたが、此この小説にはそれから先の事を書いたからそれからである。「三四郎」の主人公はあの通り単純であるが、此主人公はそれから後の男であるから此点に於ても、それからである。此主人公は最後に、妙な運命に陥おちいる。それからさき何どうなるかは書いてない。此意味に於てもまたそれからである。
「それから」予告(青空文庫)
「自己本位」の追求。そして、ユーモアの消滅。
「それから」以降の漱石の作品は大きく変化していきます。
一切のユーモアが無くなっているのです。
そして、これまでの作品は確固たる倫理観が貫かれていたのですが、不貞、自殺などの人生の暗部を描くようになっていきます。
当時の文学の主流である自然主義のテーマに合致してきたため
文壇での評価は、むしろ高まっていくのです。
さらに「それから」の続編「門」の連載が、1910年(明治43年)に始まります。
ところが、連載途中から、漱石の胃潰瘍が悪化し、連載終了と共に療養を余儀なくされます。
伊豆の修善寺、菊屋旅館で転地療養しますが、生死の間を彷徨う危篤状態(修善寺の大患)に陥る事態となります。
1912年(大正元年)、執筆ができるまで持ち直した漱石は「彼岸過迄」の連載を始めます。
その、題名のつけ方がとても漱石らしいです。
「彼岸過迄」というのは元日から始めて、彼岸過まで書く予定だから単にそう名づけたまでに過ぎない実は空しい標題である。かねてから自分は個々の短篇を重ねた末に、その個々の短篇が相合して一長篇を構成するように仕組んだら、新聞小説として存外面白く読まれはしないだろうかという意見を持していた。この「彼岸過迄」をかねての思わく通りに作り上げたいと考えている。
「彼岸過迄」(青空文庫)
1913年(大正2年)には、「行人」、
そして、1914年(大正3年)に、「こころ」を連載します。
1916年(大正5年)、「明暗」執筆途中に自宅で死去。50歳のときでした。
漱石の人生を踏まえて、作品を読むと、味わいがより深まるハズです。
漱石の人生を振り返る機会を増やすために、解説付き読書会を毎年開催したいと考えています。