
太宰治の「東京八景」を読むと、太宰治がなぜ戯作を書くのかがよく解る
- 日本文学
掲載日: 2025年11月16日
太宰治の作品で、誰もが頭に浮かぶのが「人間失格」でしょう。とはいうものの、最初に読んだ太宰作品が「人間失格」だと、太宰に嫌悪感を抱いてしまうかもしれません。
かくいう私もそうでした。
大学生の頃、「人間失格」を読んで以来、あまりに自堕落な人物像に嫌悪感を抱いてしまい、その後ずっと太宰作品を避けてきました。
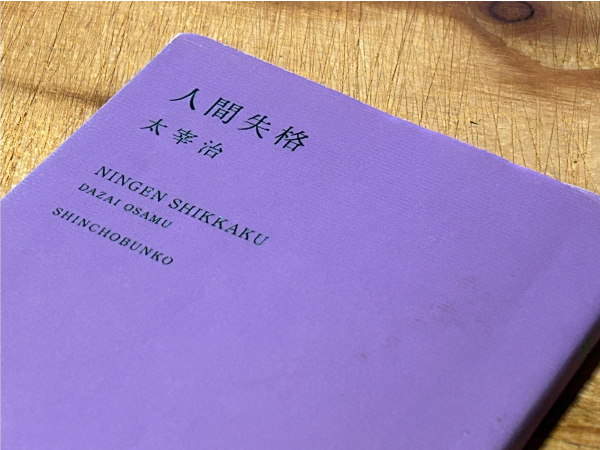
そして時は流れ、社会人になって、読書会に参加するようになった頃、友人からの勧めで「魚服記」を読んでみました。「魚服記」は太宰治が弱冠26歳にして発表した短編小説です。
いや、実に面白い。
→「魚服記」についてのコラムはこちらから。
なぜ、太宰は、「人間失格」のような悲壮な自伝的小説を書く一方で、「魚服記」のように実に面白い小説、戯作を描くのでしょうか。
もう一つ謎があります。
「魚服記」収められている太宰の自選短編集の題名は「晩年」です。
なぜ弱冠26歳の若き青年が、死を連想させるような題名にしたのでしょうか。
この二つの謎は、「東京八景」を読むと、わかるのです。
『東京八景』は、こんな小説です。
『東京八景』は、昭和16年(1941年)1月に文芸雑誌『文学界』に掲載された私小説。太宰治が32歳の頃の作品です。
太宰治が、帝国大学に入学するために上京し、その後の10年間の東京暮らしを描いています。絶望のどん底に落ちていく姿が、とても痛々しいです。
『東京八景』を読み解いていきましょう。
この物語の主人公「私」が伊豆の山村にある安宿に就いたところからこの物語は始まります。
彼は貧しい作家でしたが、結婚し収入も得られるようになってきました。すくなくとも向こう一か月ぐらいはお金の心配はしなくて済むと思えるようになってきたのです。
そんな心境の今、書きたいものだけを、書いて行きたいと思い、東京での十年間のことを、書き残しておきたいと思い、その執筆のためにこの安宿に来ました。

東京八景。私は、その短篇を、いつかゆっくり、骨折って書いてみたいと思っていた。十年間の私の東京生活を、その時々の風景に託して書いてみたいと思っていた。
(中略)
東京八景。私はそれを、青春への訣別の辞として、誰にも媚びずに書きたかった。
(中略)
東京八景。私は、いまの此の期間にこそ、それを書くべきであると思った。いまは、差し迫った約束の仕事も無い。百円以上の余裕もある。
太宰治『東京八景』(青空文庫より)
「東京八景」と続くリフレーンが、詩のようで、読んでいて気持ちがいい文章です。
そして彼は、その日の夜から執筆を始めます。
まずは暗い電燈の下で、東京市の地図を広げて、これまでも人生を振り返ってゆきます。
戸塚。──私は、はじめ、ここにいたのだ。
彼が東京帝大の仏蘭西文科に入学し、初めて東京にやってきて居を構えたのが、戸塚の下宿です。
学校へはほとんど行かず、左翼活動に精を出していた時期です。
そして郷里から芸妓上がりの女、Hを呼び寄せます。
ところが、実家では彼の行く末を心配しており、その結果・・・、
兄は、女を連れて、ひとまず田舎へ帰った。女は、始終ぼんやりしていた。ただいま無事に家に着きました、という事務的な堅い口調の手紙が一通来たきりで、その後は、女から、何の便りもなかった。
太宰治『東京八景』(青空文庫より)
彼は絶望します。そして・・・、
銀座裏のバアの女が、私を好いた。好かれる時期が、誰にだって一度ある。不潔な時期だ。私は、この女を誘って一緒に鎌倉の海へはいった。
太宰治『東京八景』(青空文庫より)
彼は、心中をするのです。そして、「女は死んで、私は生きた。」のです。
彼は、留置場に入れられ取調べの末、起訴猶予になります。

五反田は、阿呆の時代である。
Hが郷里より戻ってきたことを契機とし、彼は五反田へ居を構えます。
が、しかし・・・、
私は完全に、無意志であった。再出発の希望は、みじんも無かった。たまに訪ねて来る友人達の、御機嫌ばかりをとって暮していた。自分の醜態の前科を、恥じるどころか、幽かに誇ってさえいた。実に、破廉恥な、低能の時期であった。学校へもやはり、ほとんど出なかった。すべての努力を嫌い、のほほん顔でHを眺めて暮していた。馬鹿である。何も、しなかった。ずるずるまた、れいの仕事の手伝いなどを、はじめていた。けれども、こんどは、なんの情熱も無かった。遊民の虚無ニヒル。それが、東京の一隅にはじめて家を持った時の、私の姿だ。
太宰治『東京八景』(青空文庫より)
その後彼は、非合法な左翼活動を続け、何度も警察に捕まり、その度に居を移します。

日本橋・八丁堀の材木屋の二階、八畳間に移った。
名前を変え、東京の中を転々とし、不安な日を過ごす彼。
その身に最悪な事が起こります。
或る日の事、同じ高等学校を出た経済学部の一学生から、いやな話を聞かされた。煮え湯を飲むような気がした。まさか、と思った。知らせてくれた学生を、かえって憎んだ。Hに聞いてみたら、わかる事だと思った。
太宰治『東京八景』(青空文庫より)
彼にとっては、ただ一人の心のよりどころであっただろうHが浮気をしていたのです。それを聞いた時の太宰の失望は並大抵ではなかったはずです。なぜならば・・・、
私はその日までHを、謂わば掌中の玉のように大事にして、誇っていたのだということに気附いた。こいつの為に生きていたのだ。私は女を、無垢のままで救ったとばかり思っていたのである。Hの言うままを、勇者の如く単純に合点していたのである。友人達にも、私は、それを誇って語っていた。
太宰治『東京八景』(青空文庫より)
太宰は、全てがイヤになってしまいます。
そして生活のすべてを打ち壊す意味で、警察に自首します。取り調べが終わって釈放された太宰は、結局、Hの元に帰るしかないのです。
帰るところは、Hの部屋より他に無い。私はHのところへ、急いで行った。侘しい再会である。共に卑屈に笑いながら、私たちは力弱く握手した。
太宰治『東京八景』(青空文庫より)
八丁堀を引き上げて、芝区・白金三光町。
何度目になるでしょう。太宰は「死」を決意します。
そして、
遺書を綴った。「思い出」百枚である。今では、この「思い出」が私の処女作という事になっている。自分の幼時からの悪を、飾らずに書いて置きたいと思ったのである。二十四歳の秋の事である。草蓬々(ほうほう)の広い廃園を眺めながら、私は離れの一室に坐って、めっきり笑を失っていた。私は、再び死ぬつもりでいた。
太宰治『東京八景』(青空文庫より)
ここからが、太宰が常人と違うところです。ボクがこんな状況に陥ったとしたら、何も手につかなくなってしまうことでしょう。
ところが・・・。なんと太宰は、書きたいことが更に出てきたというのです。
小さい遺書のつもりで、こんな穢い子供もいましたという幼年及び少年時代の私の告白を、書き綴ったのであるが、その遺書が、逆に猛烈に気がかりになって、私の虚無に幽かな燭燈(ともし)がともった。死に切れなかった。その「思い出」一篇だけでは、なんとしても、不満になって来たのである。どうせ、ここまで書いたのだ。全部を書いて置きたい。きょう迄の生活の全部を、ぶちまけてみたい。あれも、これも。書いて置きたい事が一ぱい出て来た。
太宰治『東京八景』(青空文庫より)
鎌倉での自殺についてを手始めに、次々に作品を執筆していきます。そして出来上がったのが「晩年」に収録されている一連の作品なのです。
身勝手な、遺書と称する一聯の作品に凝っていた。これが出来たならば。そいつは所詮、青くさい気取った感傷に過ぎなかったのかも知れない。けれども私は、その感傷に、命を懸けていた。私は書き上げた作品を、大きい紙袋に、三つ四つと貯蔵した。次第に作品の数も殖えて来た。私は、その紙袋に毛筆で、「晩年」と書いた。その一聯の遺書の、銘題のつもりであった。もう、これで、おしまいだという意味なのである。
太宰治『東京八景』(青空文庫より)
これで「晩年」というタイトルの謎が解明しました。
さて、ここまで読んできて、ふと気がついたことがあります。
太宰は、これまでずっと、家族を安心させるためだけに嘘をついてきました。大学を卒業する、と嘘をついてきました。まるで卒業をする気持ちもないにもかかわらずです。
Hにも、私は近づく卒業にいそいそしているように見せ掛けたかった。新聞記者になって、一生平凡に暮すのだ、と言って一家を明るく笑わせていた。どうせ露見する事なのに、一日でも一刻でも永く平和を持続させたくて、人を驚愕させるのが何としても恐しくて、私は懸命に其の場かぎりの嘘をつくのである。
太宰治『東京八景』(青空文庫より)
ボクは、「晩年」に収められている「思い出」をもう一度読んでみました。「思い出」を精読してハタと思い当たりました。それは太宰が「道化」を演じているということ。
幼い頃から、太宰は使用人たちの前で「道化」を演じることで、皆に気に入られることを体験してきました。太宰は、懺悔をするかのように悲壮な私小説を書き続ける一方で、「走れメロス」や「女生徒」のような巧みに練り上げられた「創作」を書き続けているのは、「道化」を演じる延長線上にあるのではないでしょうか。
サーカスでピエロがバナナの皮を踏んで滑って転ぶシーンがあります。それを観客からの遠目で見るとオモシロい喜劇ですが、実際に滑って転んでいる当人にとっては、痛いし惨めだし、悲劇以外の何物でもありません。ピエロは、目の下に涙が一滴落ちるメイクをしています。それは、人を笑わせる演技をしていても心の底では泣いていることを表現しているのです。

「東京八景」と「思い出」を読んだ後で、太宰治の作品を読むと、それまで抱いていたイメージとまるで違ってくることだと思います。








