
フランツ・カフカ「掟の門」はアナタの人生の登竜門なのかもしれない。
- 海外文学
掲載日: 2023年04月14日
「掟の門」は、1914年、カフカが31歳の時に発表された短編小説。
同時期に長編「審判」を執筆しています。
「掟の門」のあらすじ
ひとりの男が「門」の前にやって来る。
門番に「入れてくれ」というが、「今はダメだ」と言われる。
門番はさらに言う。
「入りたいのなら、俺にかまわず入ればいい。
ただし、この先には、俺よりももっと強い門番がいる」
男は門の中に入ることをためらう。そして長い年月が経つ。
男は臨終の間際に、ふとあることに気が付く。
自分以外には誰一人として、中に入ろうとした者がいなかったのだ。
男は薄れていく意識の中で門番の声を聴く。
「誰一人ここには来ない。この門はお前だけのものなのだ。さぁ、門を閉めるとしよう」

「掟の門」とは、いったい何?
「掟の門」を執筆していた頃、カフカは恋人フェリーツェ・バウアーとの結婚が現実のものとなりつつあり、悩んでいました。
文筆の時間が取れなくなることを恐れていたのです。
結婚に進むか、それとも、立ち止まるか・・・。
結局は、婚約を解消する道を選ぶカフカ。
カフカの境遇を踏まえると、カフカの言わんとすることが見えてきませんか?
読書会では、こんな解釈もありました。
2025年2月8日に、「フランツ・カフカの推し作品を語る読書会」を開催しました。
ご参加いただいた方の解釈がとても興味深いものだったので、ここでご紹介しておきます。
その方はドイツ在住の日本人の方。
ドイツという異国の地にいると、この作品の主人公が門をすすめない心境が痛いほどよくわかるとのこと。
つまり、この門をドイツ人のコミュニティへの門として考えると、踏み込んだとしても決して相いれない世界が待っているはずで、とても進めないと実感したそうです。
ましてや、門の先には更に強い門番が待っているなんて言われると、とてもじゃないが先へはいけないとおっしゃってました。
この作品は、読んだ人なりのいろんな解釈ができる、とても優れた寓話なのだと思います。
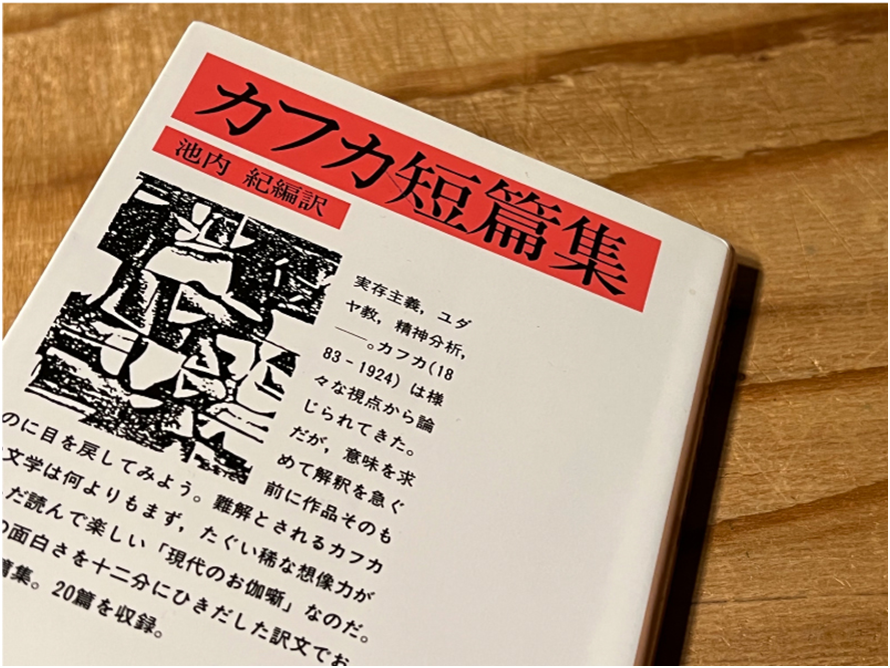

〇フランツ・カフカをモチーフにしたTシャツ、パーカーなどのグッズを絶賛発売中です。→https://suzuri.jp/bngk_com/designs/7886809









