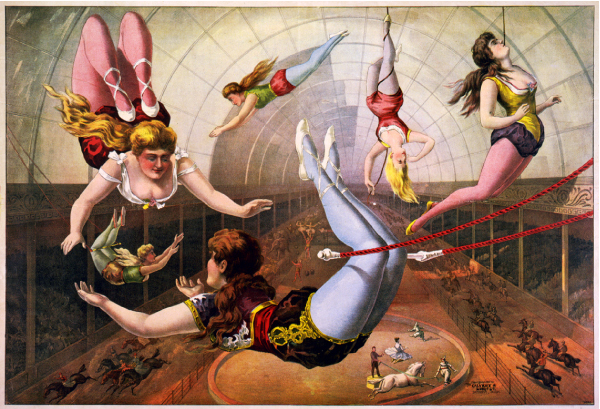北杜夫「岩尾根にて」は、登山に取りつかれている男の心象風景を描いているのだろうか。
- 日本文学
掲載日: 2024年05月17日
「岩尾根にて」は、1956年に、文芸雑誌「近代文学」1月号に掲載された短編小説。岩尾根を歩く主人公が体験する不思議な出来事を描いています。
主人公の「私」の一人称で物語は進みます。
「私」は、石の破片が散乱しているチムニー(岩壁上の割れ目)の根元にいます。
以前、二人の仲間を失って以来、山から遠ざかっていた「私」は、数年の間、岩らしい岩には接していなかったのです。
「私」は岩壁の下から離れ、崩れ落ちた岩の細片の上を、元来た方へ辿り始めます。
すると足元の石に一匹の黒蝿が止まるのを目にします。
歩を進めるにつれ増えていく蠅。
やがて「私」は、登山道から外れた場所で、胡麻粒のように蠅がたかっている死体を目にするのです。
反射的に飛び下がり、元の登山道に戻ります。
ふと、遠方になった岩場に人影を発見します。
双眼鏡で見ると、ザイルもつけずに大型のザックを背負ったまま岩肌にしがみついている男がいました。
私には相手の鼓動までが聞き取れるようで、覗いているのが苦痛だった。(中略)やめろ、やめろと、私は心の中で呟いていた。
「岩尾根にて」/新潮文庫「夜と霧の隅で」より
その後、2時間ばかりかけて山頂に到着した「私」は、尾根を進む。
足許からの風を受けながら「私」は、不思議な気持ちにとらわれます。
私は両側の谷間を一目で見渡すことのできる剣の刃のような尾根道を辿っているのだったが、同時に這松の中に横たわって蠅にたかられてもいたし、一枚岩にとりついて手掛かりを探してもいた。(中略)その差異がゆらぎ、霧のように溶け、重なり合い、一つの私になった。
「岩尾根にて」/新潮文庫「夜と霧の隅で」より

ここから、現実と思考の世界が入り混じってくるような展開になっていきます。
歩くうちに、彼方に人影が見え、一人の男が岩に腰を掛けています。
「こんにちは」とその男が言いますが、果たして彼が唇を動かしてそういったかはわからないのです。
そして、コーヒーを炒れてもらい飲むのです、が・・・。
このコーヒーを作ったのは私ではないかという錯覚がこみあげてきた。
「岩尾根にて」/新潮文庫「夜と霧の隅で」より
ここまで読み進めるうちに、この物語は、主人公の「私」が抱いている心象風景のような気がしてきました。
何かに取り憑かれたように岩壁を危なげに登る不安、そして、墜落して死ぬ恐怖。
そういった思惑が、主人公が遭遇する出来事として描かれているのではないでしょうか。
そう考えると、最後に繰り返し出てくる「ゆっくり行きましょう」という言葉が、実にしっくりくるのです。