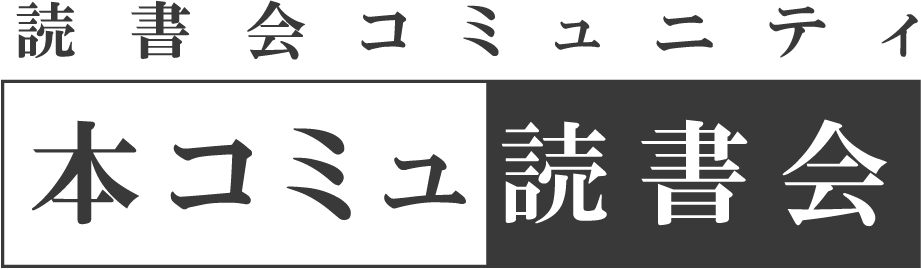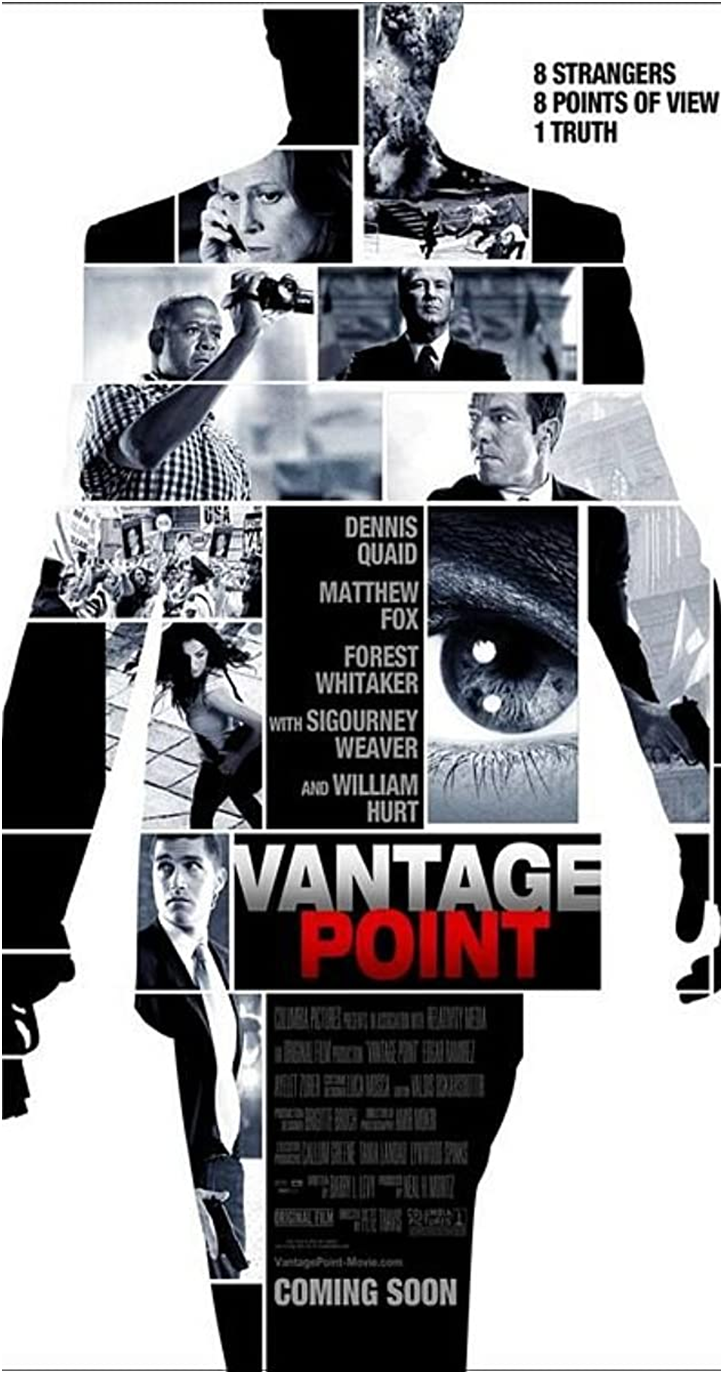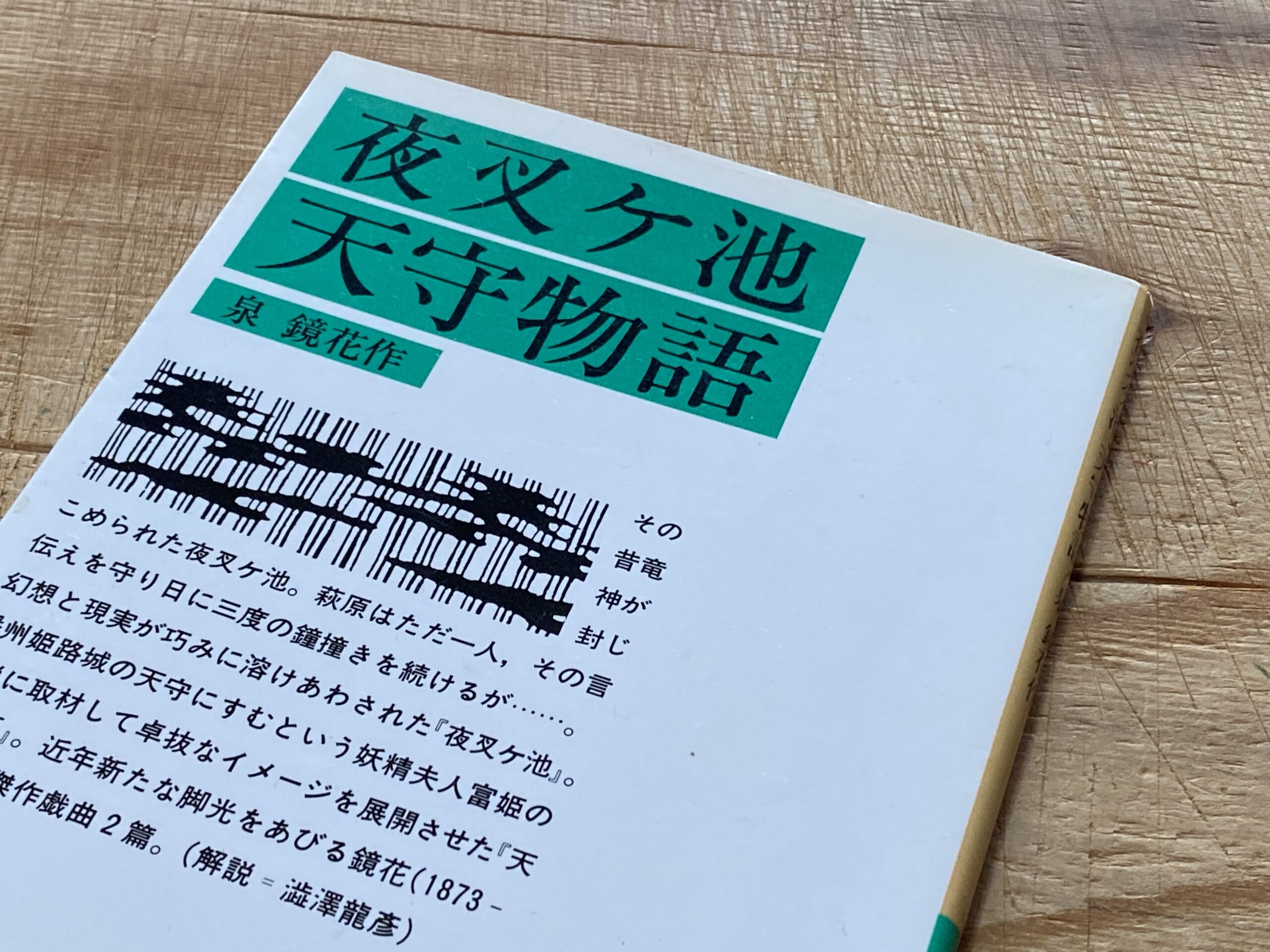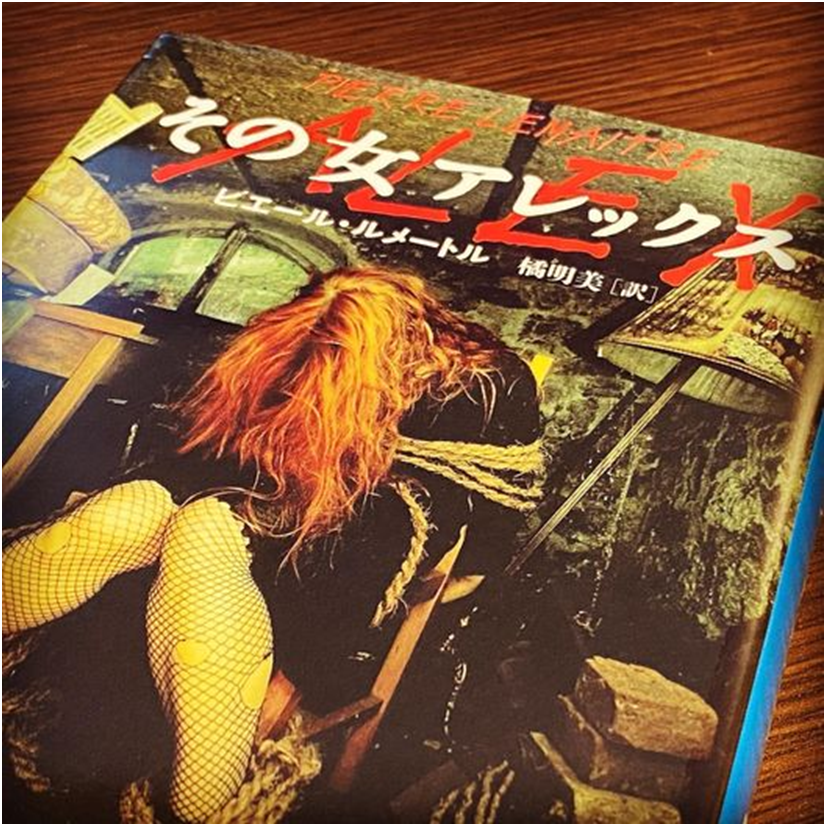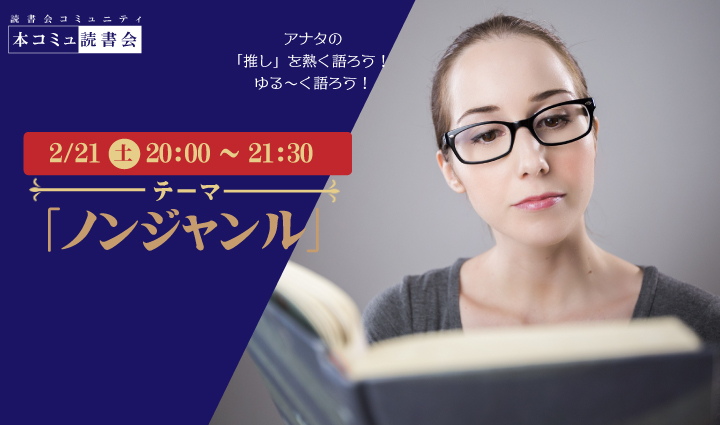坂口安吾のエッセイ『FARCEに就いて』を読むと、なぜ安吾がファルス小説を書いたかがよく解る。
- 日本文学
掲載日: 2025年07月23日
坂口安吾は、1931年(昭和6年)に発表したファルス小説『風博士』が、評判となり一躍文壇に躍り出ることになります。
『FARCEに就いて』は、その翌年1932年(昭和7年)に文芸誌「青い鳥」に掲載されたエッセイ。
「ファルス」とは、「道化」「笑劇」を意味し、ファルス小説は、落語の小話のように下ネタありお色気ありのいたって能天気な小品。読者を楽しませることを目的とした作品ジャンルです。
そんな「ファルス」について、安吾はどのようなことを言いたいのでしょうか。
『FARCEに就いて』を読んでいきましょう。
冒頭はこんな文章で始まります。
芸術の最高形式はファルスである、なぞと、勿体振つて逆説を述べたいわけでは無論ないが、然し私は、悲劇や喜劇(コメディ)よりも同等以下に低い精神から道化(ファルス)が生み出されるものとは考へてゐない。
(中略)
私の所論が受け容れられる容れられないに拘泥なく、一人白熱して熱狂しやうとする――つまり之が、即ち拙者のファルス精神であります。
坂口安吾『FARCEに就いて』(青空文庫)
ファルス小説が一番とは言わないが、悲劇や喜劇よりも低くみられるのはおかしい。世間一般に受け入れられるかどうかは関係なく、自分のファルスに対しての考えを述べるだけだと、安吾は釘を刺しています。
おそらくは、この後にちょっと由々しきことを書くことが示唆されていますね(;^_^A
安吾は続けます。
私が最初に言ひたいことは、特に日本の古典には勝れた滑稽文学が存外多く残されてゐる、このことである。私は古典に通じてはゐないので、私の目に触れた外にも幾多の滑稽文学が有ることとは思ふが、日頃私の愛読する数種を挙げても、「狂言」、西鶴(好色一代男、胸算用等)、「浮世風呂」、「浮世床」、「八笑人」、「膝栗毛」、平賀源内、京伝、黄表紙、落語等の或る種のもの等。
一体に、わが国の古典文学には、文学本来の面目として現実を有りの儘に写実することを忌む風があつた。
坂口安吾『FARCEに就いて』(青空文庫)
明治以前には、戯作の傑作が沢山ありました。ところが明治維新で戯作は完全否定されて、西洋からの文学がよしとされてしまいます。
それは現実をリアルに描く自然主義文学。
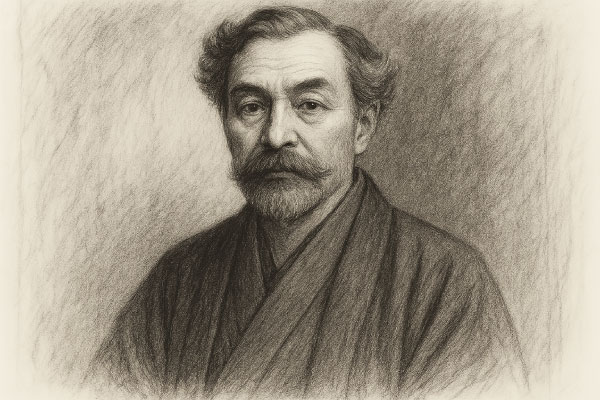
安吾は、文学の主流であった自然主義文学をけなします。
写実よりは実物の方が本物だからである。単なる写実は実物の前では意味を成さない。単なる写実、単なる説明を文学と呼ぶならば、文学は、宜しく音を説明するためには言葉を省いて音譜を挿み、蓄音機を挿み、風景の説明には又言葉を省いて写真を挿み、そして宜しく文学は、トーキーの出現と共に消えてなくなれ。単に、人生を描くためなら、地球に表紙をかぶせるのが一番正しい。
坂口安吾『FARCEに就いて』(青空文庫)
さて、そこでファルスの出番です。
大体人間といふものは、空想と実際との食ひ違ひの中に気息奄々として(拙者なぞは白熱的に熱狂して――)暮すところの儚ない生物にすぎないものだ。この大いなる矛盾のおかげで、このべらぼうな儚なさのおかげで、兎も角も豚でなく、蟻でなく、幸ひにして人である、と言ふやうなものである、人間といふものは。
坂口安吾『FARCEに就いて』(青空文庫)
現実とかけ離れた「空想」を抱くことこそ人間たるゆえんだと安吾は言います。
「感じる」といふこと、感じられる世界の実在すること、そして、感じられるといふ世界が私達にとつてこれ程も強い現実であること、此処に実感を持つことの出来ない人々は、芸術のスペシアリテの中へ大胆な足を踏み入れてはならない。
ファルスとは、最も微妙に、この人間の「観念」の中に踊りを踊る妖精である。現実としての空想の――ここまでは紛れもなく現実であるが、ここから先へ一歩を踏み外せば本当の「意味無しナンセンス」になるといふ、斯様な、喜びや悲しみや歎きや夢や嚔くしゃみやムニャ/\や、凡有あらゆる物の混沌の、凡有ゆる物の矛盾の、それら全ての最頂天に於て、羽目を外して乱痴気騒ぎを演ずるところの愛すべき怪物が、愛すべき王様が、即ち紛れなくファルスである。
坂口安吾『FARCEに就いて』(青空文庫)
一歩間違えれば、意味のない絵空事になるところを微妙に踏みとどまって読者を楽しませることができるのが「ファルス」なのです。
ファルスとは、人間の全てを、全的に、一つ残さず肯定しやうとするものである。凡そ人間の現実に関する限りは、空想であれ、夢であれ、死であれ、怒りであれ、矛盾であれ、トンチンカンであれ、ムニャ/\であれ、何から何まで肯定しやうとするものである。ファルスとは、否定をも肯定し、肯定をも肯定し、さらに又肯定し、結局人間に関する限りの全てを永遠に永劫に永久に肯定肯定肯定して止むまいとするものである。諦めを肯定し、溜息を肯定し、何言つてやんでいを肯定し、と言つたやうなもんだよを肯定し――つまり全的に人間存在を肯定しやうとすることは、結局、途方もない混沌を、途方もない矛盾の玉を、グイとばかりに呑みほすことになる
坂口安吾『FARCEに就いて』(青空文庫)
ファルス小説は、人間のあらゆる空想を肯定して描き出します。すべてを描き出すことこそファルスの真骨頂なのです。
『風博士』を書いた意図とは。
安吾のファルス小説『風博士』を、何の予備知識もなく読み始めると、あまりにも支離滅裂なナンセンスなエピソードが続くので、間違いなくなんじゃこれ?という感想を抱くことでしょう(;^_^A
そんな感想を持った方は、エッセイ『FARCEに就いて』を読んでみてください。
なんとなく安吾の言わんとするところがわかるのではないでしょうか。
人はどれだけナンセンスなことが描けるのか、そしてあなたはこのナンセンスさをどこまで肯定できる、つまり笑い飛ばすことができるのでしょうか、と安吾が問いかけているような気がしませんか?