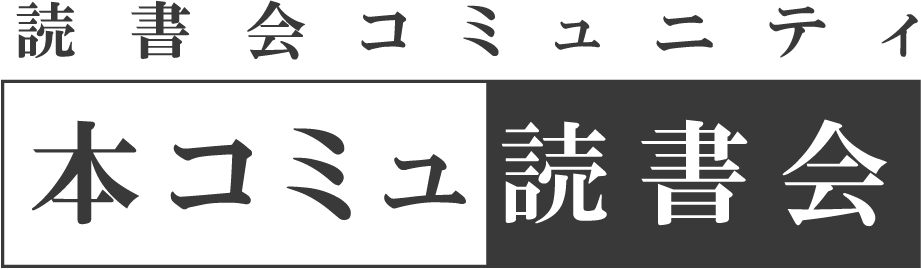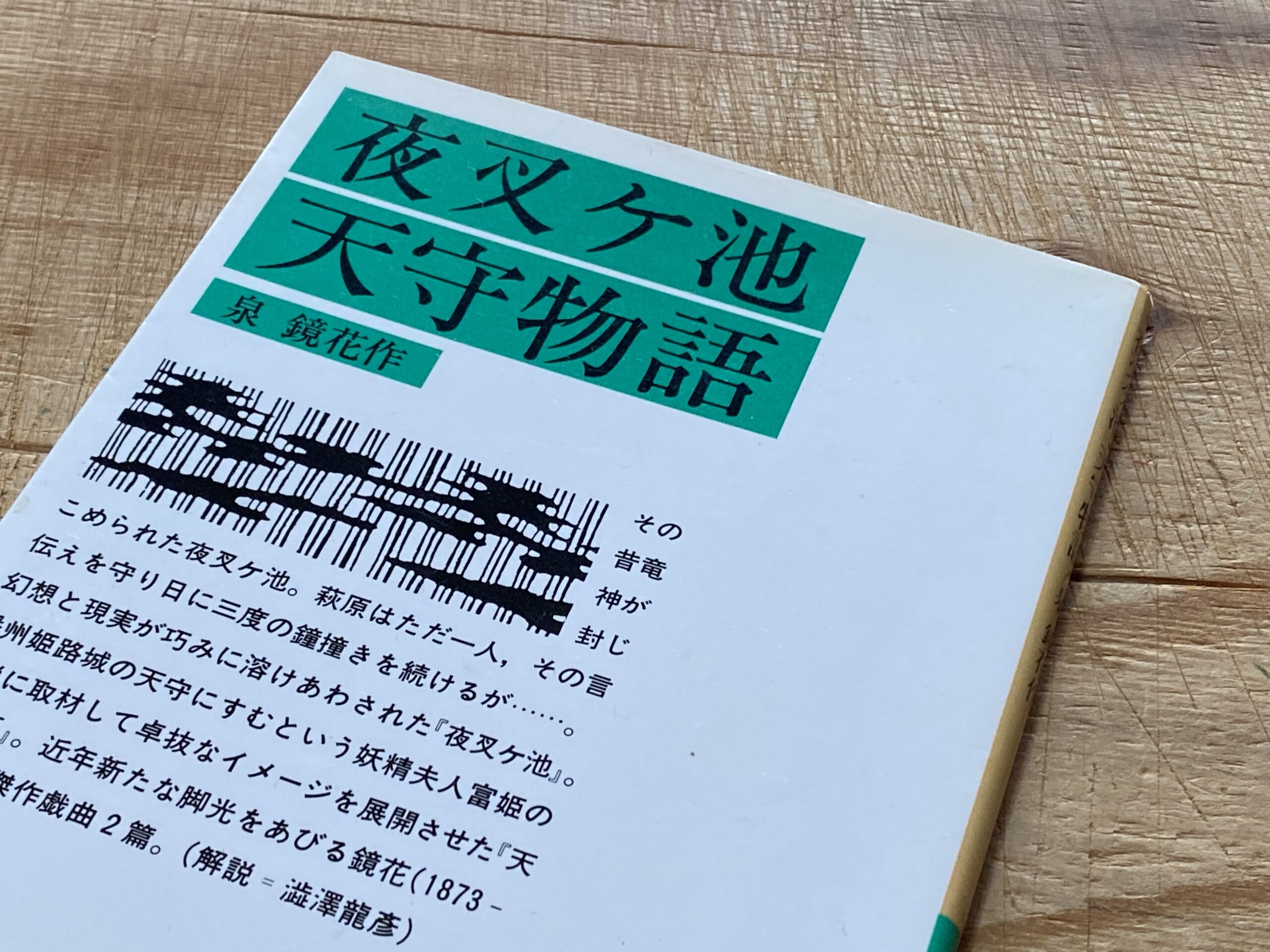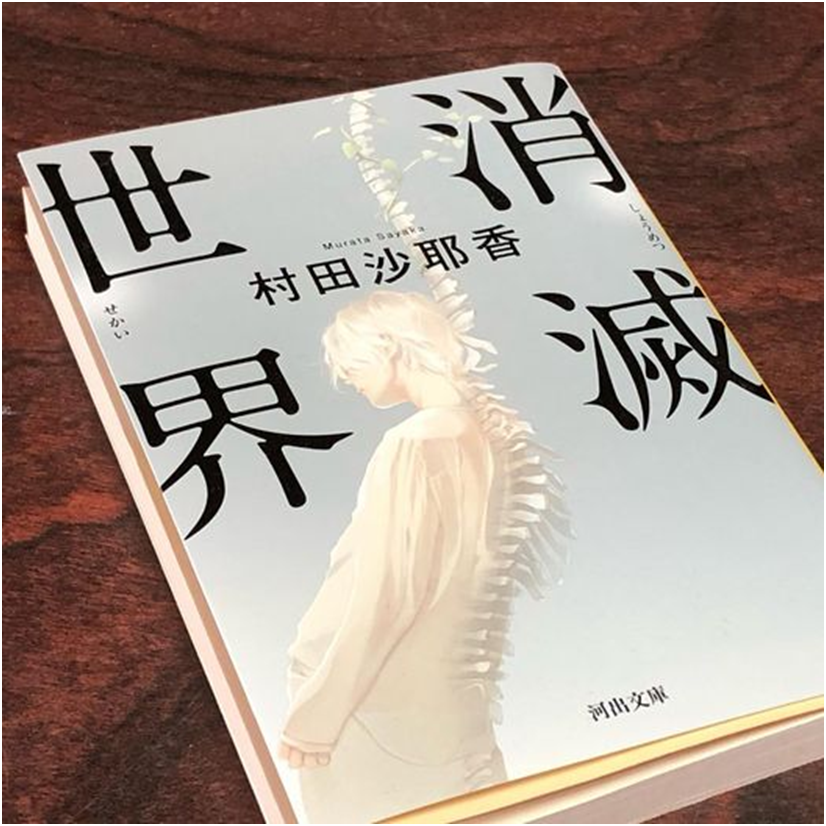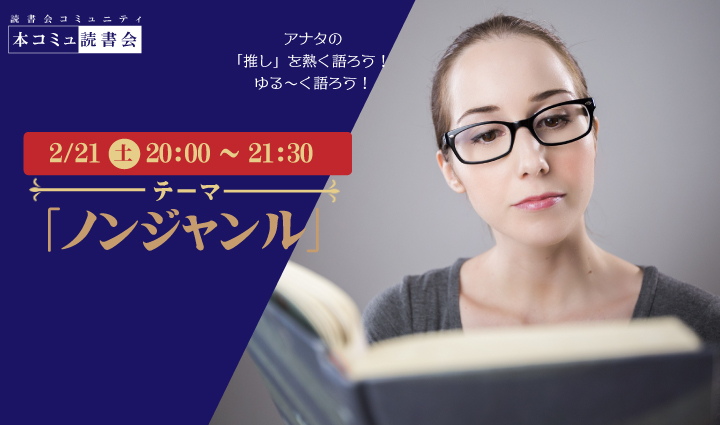フランツ・カフカ「万里の長城」は、古代中国の皇帝にまで話が及ぶ、実に壮大な作品です。
- 海外文学
掲載日: 2025年02月08日
「万里の長城」は、カフカが34歳の時(1917年)に執筆されたエッセイ。
カフカ存命中は、どこにも発表されていない作品です。
前年の1916年には、代表作である「変身」が発表されています。
「変身」は、ある朝目覚めると虫になってしまった男の話。幻想的で不条理な作品です。
カフカというと、誰もが思い浮かべるイメージは、まさに「変身」のような作品。
そんなイメージで「万里の長城」を読むと、ビックリするでしょう。
「万里の長城」はこんな作品です
この作品は小説ではありません。如何にして万里の長城が建設されたかを分析する論文です。
冒頭では、万里の長城が「工区分割方式」で建設されたということが明かされます。
端から順番に壁を建設したのではなく、20名ほどの労働者が班を組み、500メートルほどの壁を建設し、それをつなぎ合わせていくというもの。
では、いったいなぜそんな方式が採用されたのか。
そこには、あまりにも長大であるが故の理由があったのです。
その理由を実に理路整然と解説しています。
そこには、不条理の「ふ」の字もありませんので、カフカ的表現を期待した方は肩透かしに会うことでしょう。
さて、話はそこに留まりません。
同じように長大な建築物である「バベルの塔」に話が及びます。
「ベベルの塔」は、「万里の長城」と違い、完成に至りません。
完成どころか崩壊してしまうのです。
なぜ崩壊したのか。
バベルの塔を実際に組み上げている労働者たちの心理状態を考慮していなかったが故のことだと言うのです。

そうなると、「万里の長城」を完成させた指導者たちの優秀さに話が及び、さらには皇帝の存在を分析するに至ります。
実に壮大な論文です。
では、この論文を書いているのは誰か。
誰の視点で描かれているのかが、明かされていきます。
「私は南東部の生まれであり、もっぱら民族の比較研究に専念してきた」とあります。
さらには「われら中国人は・・・」という記述もあります。
この論文は、ある中国人が記述した、という体で書かれている架空の論文なのです。

カフカの作品に大きな影響を受けたボルヘス。
彼が書いた諸作品にも架空の論文の体で書かれた作品が散見されるのが、これで納得できました。

〇フランツ・カフカをモチーフにしたTシャツ、パーカーなどのグッズを絶賛発売中です。→https://suzuri.jp/bngk_com/designs/7886809