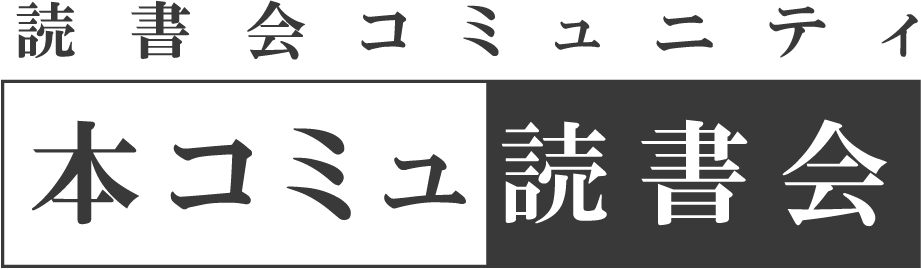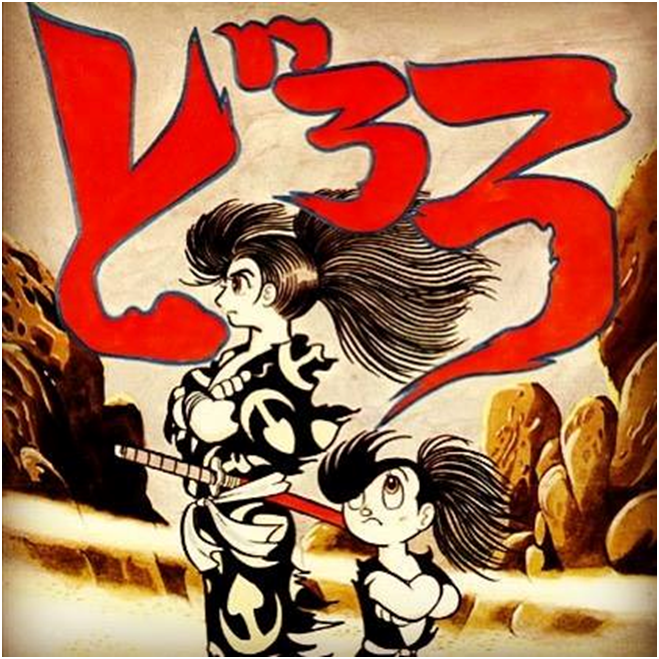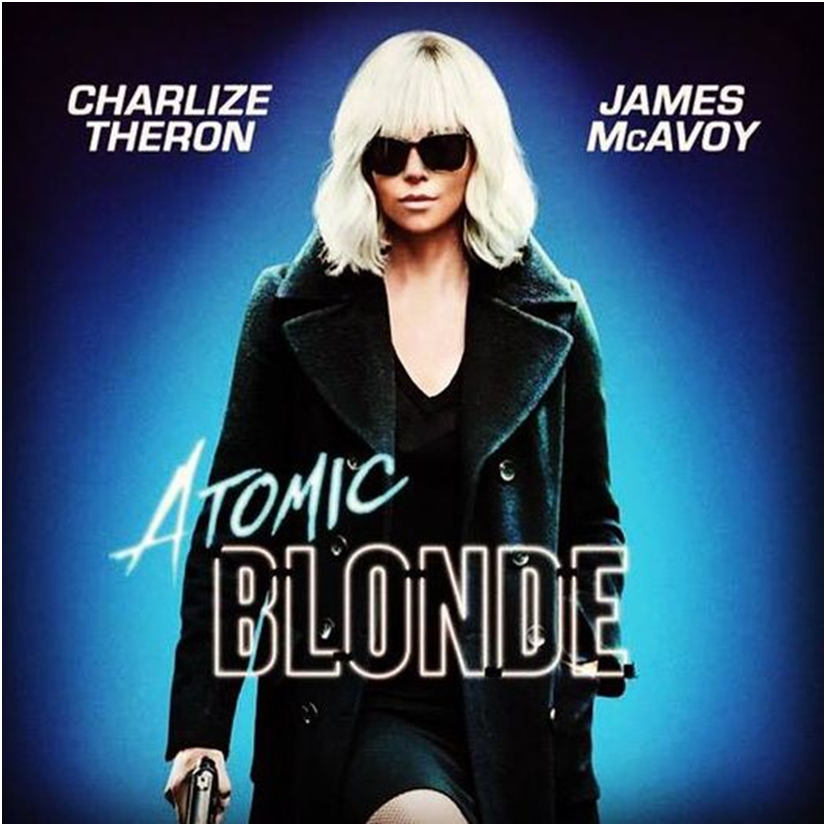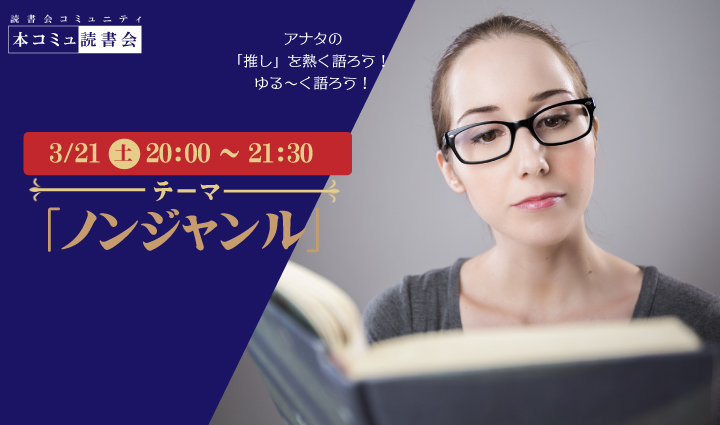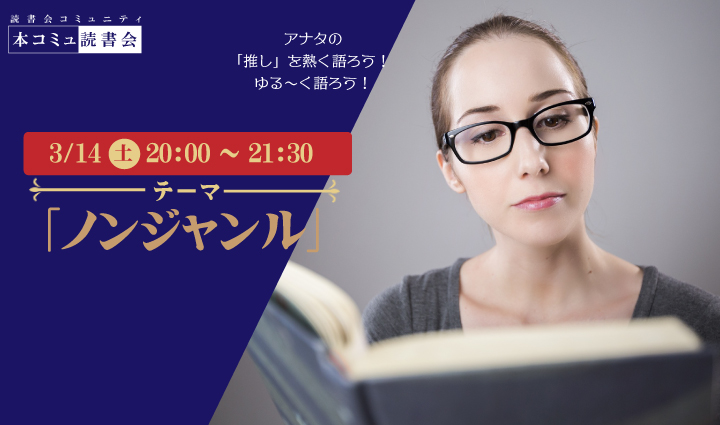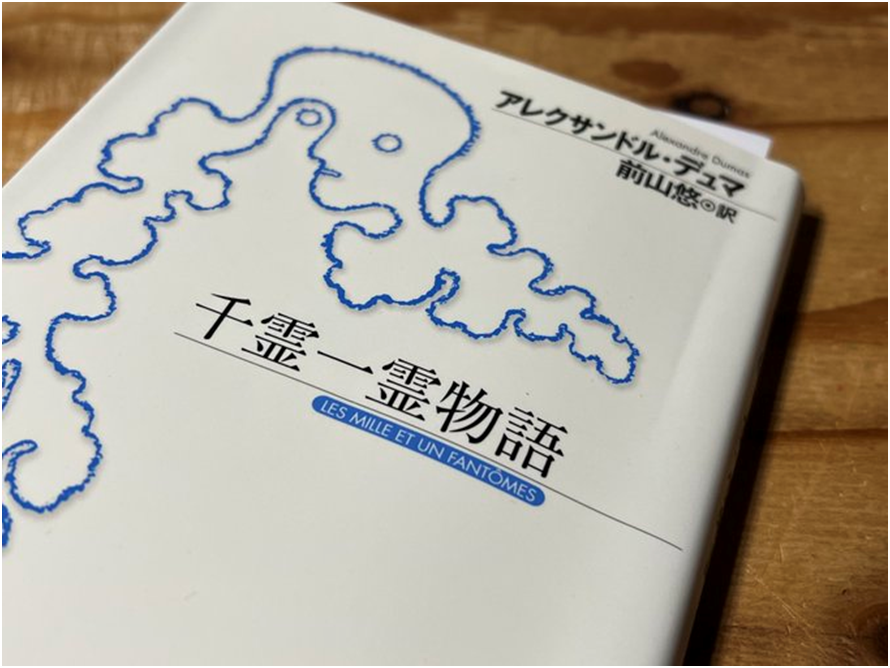
フランス革命当時の世相がリアルにわかる、アレクサンドル・デュマ「千霊一霊物語」
- 海外文学
掲載日: 2022年10月14日
「千霊一霊物語」は、1849年に刊行された、連作短編小説。
サロンに集まった人々が、それぞれが体験した、不思議な出来事を語るという「枠物語」です。
アレクサンドル・デュマは、歴史を基にして、フィクションを巧みに加えていく作風で知られており、ストーリーがとてもリアルです。
「千霊一霊物語」のベースにあるのは、フランス革命後の出来事。
当時を生きたデュマが描くので、風化していないリアルさが漂います。
事の発端は・・・。
サロンに集まった人々に、
妻を殺したので捕まえてほしいと怯えながら訴える男。
斬首された妻の首が喋ったとのこと。
そんな馬鹿なと、人々は言う。
ところが、よくよく考えると、
いや、あながち本当かもしれない、実は、こんなことがあってね・・・。
と、順繰りに経験した怪談話を始めるのです。
読む前からワクワクしてしまいますねぇ(;^_^A
犯行現場に居合わせた人が調書のため名乗りを上げることに。
市長のルドリュ。
学者のアリエット。
司祭のムール。
医師のセバスチャン。
そして劇作家のデュマ。
そう、デュマ本人が物語の中に登場するという
とても面白い作りになっています。

1人目の語り手は、市長のルドリュ。
彼は、シャルロット・コルデーが断頭台で処刑される現場に居合わせ、そこで見たことを語り始める。
なんともおぞましい出来事ですが、デュマの文章が巧みで
どこまでが史実で、どこまでが創作なのかが混然一体となってしまい
ものすごくリアルです(;^_^A
市長ルドリュの話はさらに続く。
話の冒頭にはこう書かれています。
「今なされた恐ろしい話は、もっと恐ろしい物語の前置きでしかない」
まさに、その通りの物語が待っていました・・・(;^_^A

2人目の語り手は、医師のロベール。
生首が喋るなんてことは、幻覚に過ぎないと思っている。
そんな彼が語るのは、幻覚から覚めなかった患者のこと。
このエピソードは
あまりひねりがなかったかなぁ(;^_^A
3人目の語り手は博物館の館長を務めるルノワール子爵。
彼はフランス革命の折、民衆が歴代国王の墓を荒らす場面に遭遇した。
彼は怒りを籠めて言う。
「何かを築き上げることのできない者は
何かを打ち壊すことで自尊心を満たすのだ」と。
これは、まさにデュマの怒りでもあるようです。
そんなルノワール子爵が語るのは、
歴代フランス国王が眠るサン・ドニ大聖堂で起こった恐ろしい出来事。
敬意を欠く愚かな民衆があろうことか自らの国王の墓を暴いていく。
それはもう、いたたまれない気持ちになってしまいます。
人間というものは、かくも愚かな存在なのでしょうか。

4人目の語り手は、ムール神父。
彼自身の身に起きた不思議な出来事を語ります。
教会に盗みに入った神をも恐れぬ大悪党と対峙した際
神父は力ずくで立ち向かいません。
「説得」のみが彼の武器なのです。
ここを読むと当時の宗教観がよくわかります。
1件落着と思いきや、大悪党が改心した後に大事件が起こることになるのです・・・。
5人目の語り手は、文学者アリエット。
彼は断言します。
「死は生命を殺すものではない。死が殺すものは記憶に過ぎない」と。
なぜなら、彼はそれを見てしまったからなのです。
そして、自らの体験を語り始めるのですが
それは悲しくも切ないお話でした・・・。
6人目の語り手は、グレゴリスカ夫人。
青白い顔をした美しい女性です。
彼女は言う。
「これは、私自身に起きたことです。
聞けばお分かりになるでしょう。
私の顔がどうしてこんなの青いのかを・・・」
デュマは、こういう意味深なセリフがとてもうまいです。
どうしても次が読みたくなってきます(;^_^A
グレゴリスカ夫人は、その昔、ある男に横恋慕を持たれていました。
やがて、その男コスタキは非業の死を遂げる。
葬儀の際、夫人はこう告げられます。
「コスタキは、あなたを愛している」
過去形の「愛していた」ではなく
進行形の「愛している」と言われることが何を意味しているか・・・。