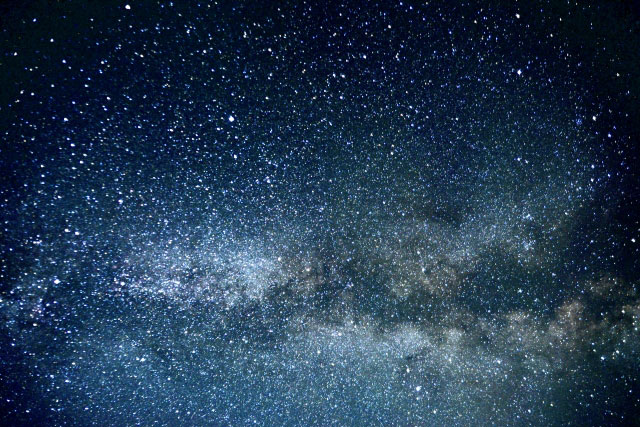朗読コンテンツ11-夏目漱石「夢十夜」-第五夜(敗軍の将が女を待つ話)は、漱石が果たせなかった夢を描いている。
- 日本文学
掲載日: 2023年01月07日
「夢十夜」とは。
「夢十夜」は、1908年(明治41年)に『朝日新聞』に連載された連作短編小説。
朗読にピッタリの長さの作品です(;^_^A 作家の人生をありのままに描く「自然主義文学」とは異なり、 リアルな「作り物」を旨としている漱石らしく、実に不思議なお話。
そして、ただの空々しい幻想的な物語ではなく、生き生きとしたリアリズムにあふれています。
今回お届けする朗読は、夏目漱石「夢十夜」の第五夜です。
「夢十夜」第五夜を解説します。
神代の昔のこと。敵の大将の前に引き据えられた敗軍の将が、
処刑される前に愛する女に会いたい、今少し待ってほしいと懇願する話です。
冒頭で敵の大将の様子が書かれています。
その頃の人はみんな背が高かった。そうして、みんな長い髯を生やしていた。革の帯を締めて、それへ棒のような剣を釣るしていた。弓は藤蔓の太いのをそのまま用いたように見えた。漆も塗ってなければ磨きもかけてない。極めて素樸なものであった。
「夢十夜」(青空文庫)
一方、敗軍の将である自分の様子はと言うと、
自分は虜だから、腰をかける訳に行かない。草の上に胡坐をかいていた。
「夢十夜」(青空文庫)
決して抗うことのできない様子が描かれています。
これは、漱石にとってどんなものなのでしょうか。
明治政府であり、世間の耳目が、あてはまるような気がします。
敵の大将は、言います。
大将は篝火で自分の顔を見て、死ぬか生きるかと聞いた。これはその頃の習慣で、捕虜にはだれでも一応はこう聞いたものである。生きると答えると降参した意味で、死ぬと云うと屈服しないと云う事になる。自分は一言死ぬと答えた。
「夢十夜」(青空文庫)
自分の運命は自分で決めろと言われています。
個人主義を貫くのかどうかです。漱石は、ここで即答しています。
個人主義で行く、と。
さらに敗軍の将はこう言います。
その頃でも恋はあった。自分は死ぬ前に一目思う女に逢いたいと云った。大将は夜が開けて鶏が鳴くまでなら待つと云った。鶏が鳴くまでに女をここへ呼ばなければならない。鶏が鳴いても女が来なければ、自分は逢わずに殺されてしまう。
「夢十夜」(青空文庫)
ところが・・・、
女は細い足でしきりなしに馬の腹を蹴っている。馬は蹄の音が宙で鳴るほど早く飛んで来る。女の髪は吹流しのように闇の中に尾を曳いた。それでもまだ篝のある所まで来られない。
「夢十夜」(青空文庫)
すると真闇な道の傍で、たちまちこけこっこうという鶏の声がした。女は身を空様に、両手に握った手綱をうんと控えた。馬は前足の蹄を堅い岩の上に発矢と刻み込んだ。
こけこっこうと鶏がまた一声鳴いた。
女はあっと云って、緊めた手綱を一度に緩めた。馬は諸膝を折る。乗った人と共に真向へ前へのめった。岩の下は深い淵であった。
蹄の跡はいまだに岩の上に残っている。鶏の鳴く真似をしたものは天探女である。この蹄の痕の岩に刻みつけられている間、天探女は自分の敵である。
果たして、女は会いにやってくるのだが、結局望は叶わなかったのです。
漱石は、生涯一人の女性と添い遂げ、文豪にしては珍しく、他の女性とのスキャンダルらしきものは皆無です。
天探女という、世間の耳目が邪魔をしたという解釈はどうでしょう。
「草枕」には、世間の耳目を「探偵」と呼び、辟易した様子が描かれています。
この物語は、いろんな解釈ができます。
読書会で、いろんな方の意見を聞きたいですねぇ。
そんな不思議な物語を朗読と映像で表現してみました。