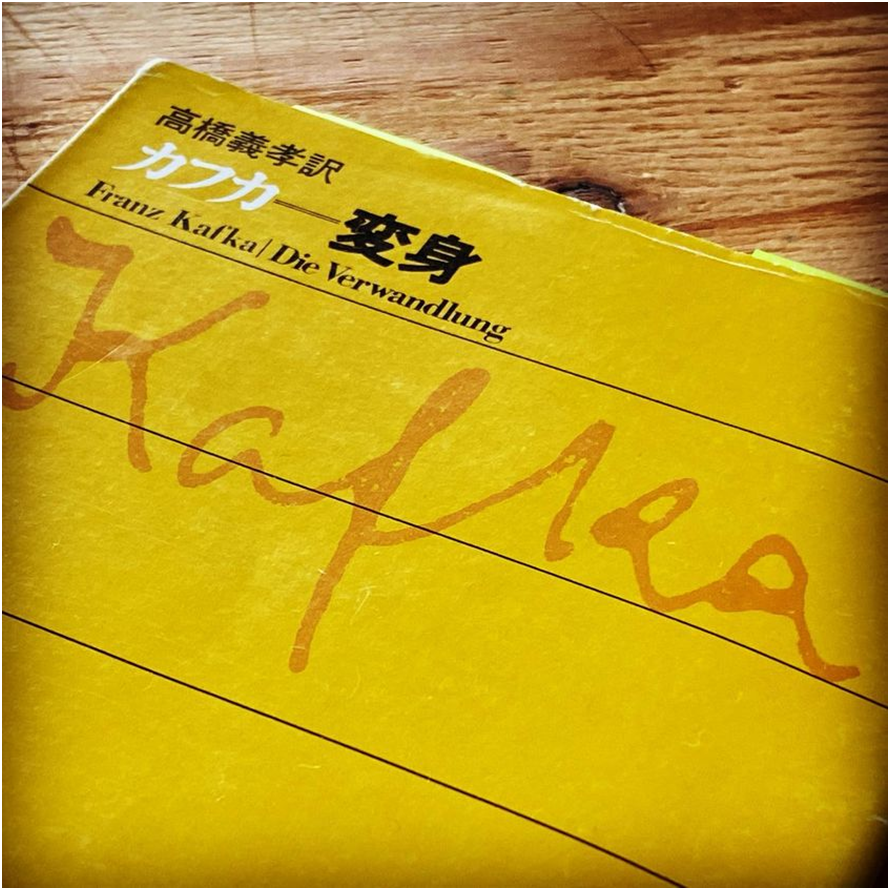泉鏡花「栃の実」は、ひと味も、ふた味も違う紀行文。
- 日本文学
掲載日: 2021年11月18日
「栃の実」は、1924年(大正13)に、文芸雑誌「新小説」に掲載された作品。
鏡花自身が福井から近江へ旅をした際の紀行文です
幻想譚でも、怪談でも、何でもありません。
が、しかし。
表現の素晴らしいこと、この上ない作品です。
例えば冒頭のこの一文。
「古の名将、また英雄が、涙に、誉に、屍を埋め、名を残した、あの、山また山、重なる峠を、一羽でとぶか、と袖をしめ、襟を合わせた」
身一つで、旅立つときの高揚感が伝わってきますねぇ。
おぼつかない足取りで出立する鏡花を、いつまでも見送り続ける車夫。
鏡花は振り返り、こう書き記します。
「翼をいためた燕の、ひとり地ずれに辿るのを、あわれがって、去りあえず見送っていたのであろう」
決して屈強な体ではない鏡花。
よほど危なげに見えたのでしょうかねぇ(;^_^A
鏡花が、旅をしたのは残暑が厳しい季節です。
日陰を作ってくれる洋傘を持たないのは、
師である尾崎紅葉が洋傘が嫌いだったから。
日差しが強い時は、扇子を使ったそうです。
一門全員がそろって扇子をかざして歩いている光景は、
風流なのか滑稽なのか微妙な光景です(;^_^A

さて、残暑の日差しが厳しい道中。
日傘もなければ扇子もない。
道端にあるのは、役にも立ちそうにない蘆(アシ)だけである。
鏡花は、こう書き記します。
「湯のような浅沼の蘆を折取って、くるくるとまわしても、何、秋風が吹くものか」
風流ですねぇ(;^_^A
旅の途中で立ち寄った茶屋。
そこの娘とのやり取りが、これまた粋な風情でとてもいいのです。
ぜひ、ご堪能ください。